住まい・世帯構成から生活保護費を自動計算
生活保護の申請方法と必要書類【はじめてでも安心】
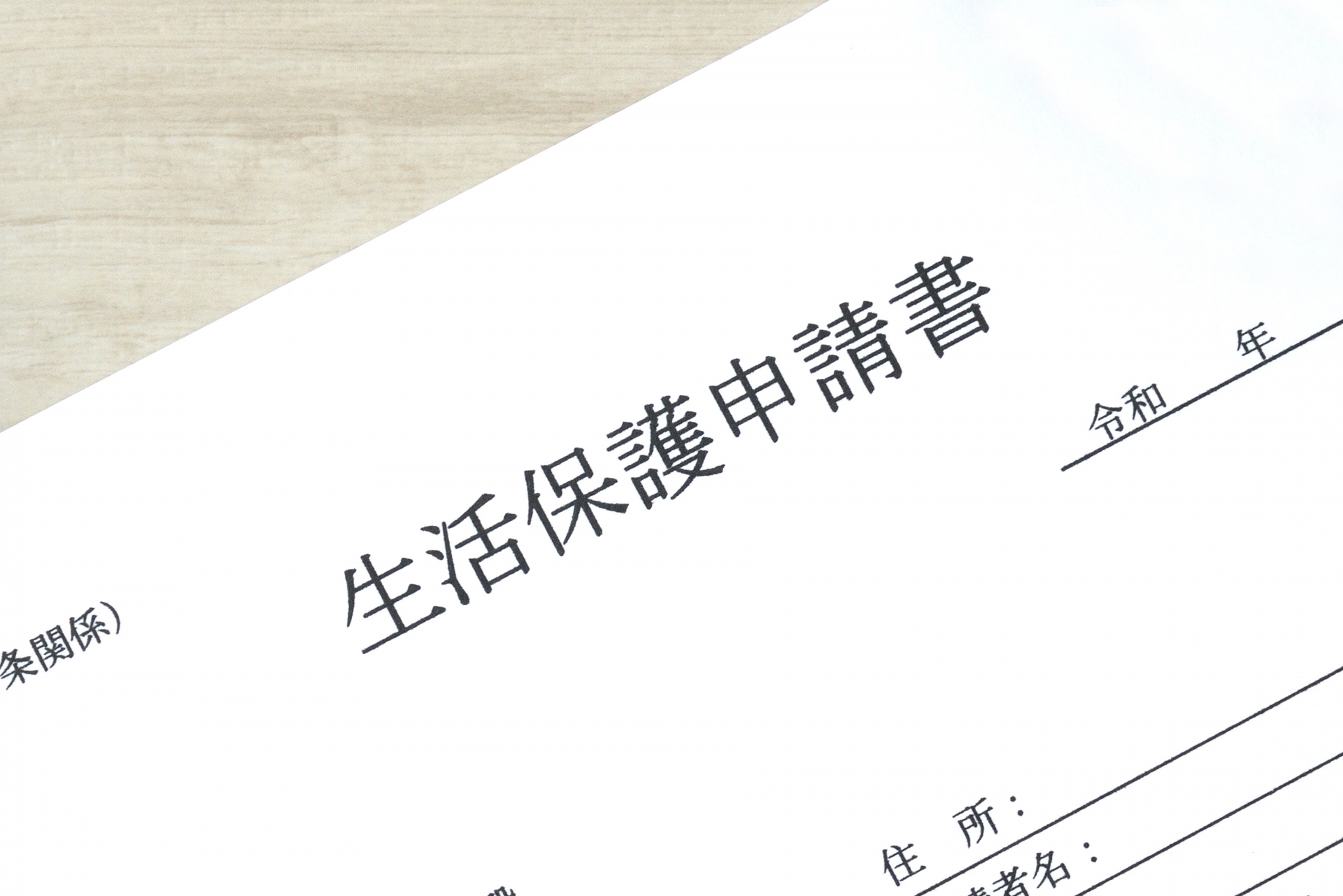
「申請の手順が分からない」「何を持っていけばいい?」──そんな不安を解消するために、生活保護の申請フローを準備→窓口→面談→家庭訪問→決定の順に解説します。緊急のときの相談先、提出時のコツ、よくある疑問もまとめました。
目次
1. 申請前の準備(まずやること)
最初に、自分の状況を簡単に整理しておくと手続きがスムーズです。
- 家計の状況:収入(給与・年金・手当・仕送りなど)と支出(家賃・光熱費・医療費など)
- 預貯金・資産:通帳、現金、有価証券、保険解約返戻金、車など
- 仕事・健康状態:就労の可否、通院の有無、障害の有無
目安をつかむには、まず保護費シミュレーションを。見込み額を知ることで不安が軽くなり、相談もしやすくなります。
2. 必要書類のチェックリスト
自治体により異なりますが、一般的には次のような書類を求められます(可能な範囲でOK)。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 健康保険証(お持ちの場合)
- 世帯全員の住民票(省略事項の指定は窓口案内に従う)
- 賃貸借契約書(住宅扶助の判断に必要)
- 収入が分かるもの(給与明細、年金振込通知、事業帳簿など)
- 預貯金通帳(過去数か月ぶん)
- 医療費・通院に関わる書類(診療明細、意見書など)
※用意できないものがあっても申請は可能。窓口で不足分の提出方法を案内してもらえます。
3. 申請窓口に行く(福祉事務所)
住所地の福祉事務所(生活保護担当)に行き、申請意思を伝えます。申請書は窓口で入手できますが、自治体サイトからダウンロードできる場合もあります。
- 同席者:不安がある場合は家族や支援団体の同席も可能です。
- 提出タイミング:原則、いつでも申請できます(窓口の受付時間に注意)。
- 申請の権利:申請を受け付けない「水際対応」は認められていません。困ったら窓口で「申請します」と明確に伝えましょう。
4. 面談(世帯状況と収入の確認)
面談では、世帯構成・収入・資産・健康状態・就労の見通しなどを確認します。特別なことを言う必要はありません。正直に、分かる範囲で答えれば大丈夫です。
- 家計の聞き取り:通帳や明細を見ながら確認
- 就労支援の説明:働ける場合は、就労支援メニューを案内
- 医療の確認:通院が必要な場合は医療扶助の手続きも
5. 家庭訪問(暮らしの確認)
必要に応じて職員が自宅を訪問し、生活状況を確認します。高価な資産がないか等の確認で、生活の実態把握が目的です。片付いていなくても問題ありません。
6. 決定までの期間と結果通知
審査には通常原則14日以内(最大30日)の期間がかかります。結果は文書で通知され、支給が決まれば保護開始日が示されます。支給は月ごとに行われ、世帯の状況に応じて調整されます。
7. 急ぎのとき(生活に困っている場合)
住まいや食事の確保が難しいなど緊急時は、その旨を窓口に伝えてください。自治体や支援団体と連携し、必要な支援につながるケースがあります。相談先一覧もご活用ください。
8. よくある質問
Q1. 仕事をしていても申請できますか?
できます。収入があっても、世帯の基準額に満たなければ支給対象です。就労と受給の両立は可能です。
Q2. 家族に知られたくない
原則として世帯単位での確認が必要ですが、事情がある場合は窓口で相談してください。DV等の事情がある場合は配慮されます。
Q3. 車を持っているが申請できる?
就労や通院に必要な場合など、一定の条件で保有が認められることがあります。個別に判断されます。
Q4. どのくらいで支給される?
審査後、支給決定がされると月単位で支給されます。急ぎの場合は窓口で事情を伝えてください。